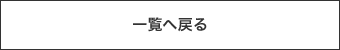2024年12月01日 更新
▶︎ 調査で新発見!
ジョルジュ・ルオー《ロシア・バレエ団のダンサー》(1929年、公益財団法人諸橋近代美術館)
本作は長らくカンヴァスに描かれているとされてきましたが、ルオーの他作品の特徴との比較から、別素材に描かれた作品である可能性が浮かび上がり、2022年に分析調査を行いました。その結果、カンヴァスに裏打ちされた「紙」に描かれていることが発覚したのです。さらには絵具が何層も複雑に重なり合っており、黒い線描部分は比較的希釈された絵具が用いられていたこともわかりました。ルオーの作品はほとんどが紙に描かれており、描いた絵を絵具が乾かぬうちに別の作品の上に重ね置き、気が向くとまた重ねた紙の束から作品を抜き取って絵具を塗り重ねるといった制作工程を経たとされています。そのため、本作でも作品を重ねたために生じた絵具の欠損や潰れ、他作品から付着したと思われる紙繊維、絵具の破片が確認できました。
見出しに戻る
▶︎ リトグラフって?
サルバドール・ダリ『ドン・キホーテ』(1957年、公益財団法人諸橋近代美術館)
本作に用いられているリトグラフという技法は、水と油の混じり合わない特性を活かして、平らな版面にインクの乗った描画部とインクの乗らない余白部をつくるものです。研磨した石版に油性インクで描画したあと、版面全体にアラビアゴムと硝酸水溶液を塗布すると、アラビアゴムと酸が版面に作用して親水性の余白部と親油性の描画部が作られます。印刷時にはアラビアゴムを洗い流し、版面に薄く水をひいた状態を保ちながら、ローラーで油性インクをつけると、インクが水分によって弾かれて親油性の描画部のみにインクが乗ります。この上に紙を置いてプレス機で刷ると、インクの飛沫や筆さばきを直接紙に描いたように再現することができます。美しく飛び散ったインクの模様や大胆な筆遣いが躍動感を与えるとともに、作品を見事に引き立てていることがうかがえます。
見出しに戻る
▶︎ 総勢80人あまりの版画師たち
ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー《ストーンヘンジ》(1829年、郡山市立美術館)
ターナーが活躍していた時代は、まだ写真が普及しておらず、特定の地域が描かれたシリーズものの版画は、旅行ガイドのような役割を担っていました。ターナーの水彩画、油彩画、デッサンをもとにした銅版画は、なんと800点以上にも及ぶとされています。自ら彫版を行うこともあったと言われていますが、その大半は腕利きの専門彫版師によるもので、携わった彫版師は80人以上もいたそうです。彫版を行う際はターナーが監督をしていましたが、彫版師に厳しく指示をしていたことから、度々口論になっていたといわれています。
見出しに戻る
▶︎ 常に新しい技法を求めて…
カミーユ・ピサロ《ポントワーズ丘陵、牛飼いの少女》(1882年、公益財団法人諸橋近代美術館)
1883年、ピサロは画家ルイ・アイエ(1864-1940)を通じて初めて点描技法を知ります。光学理論に基づき、網膜における視覚混合を利用した本技法は、印象主義には希薄な客観性を獲得するためにうってつけの表現方法でした。1885年、ピサロはギヨマンのアトリエでポール・シニャック(1863-1935)と出会います。その翌年には第8回印象派展にシニャックを招待し、以降ピサロはシニャックと密接に協力し合い点描技法を追求していきます。
見出しに戻る
▶︎ 「近代絵画の父」の初期作品
ポール・セザンヌ《林間の空地》(1867年、公益財団法人諸橋近代美術館)
セザンヌの初期作品の特徴の一つである厚塗りによる描写は、本作にも施されています。パレットナイフを用いたこの技法は、レアリスムの画家ギュスターヴ・クールベの作品から倣ったことが指摘されていますが、セザンヌはクールベ本人から直接パレットナイフの技法を教わっておらず、1867年のパリ万国博覧会と併せて開催されたクールベの個展で彼の油彩作品を目にしたことをきっかけにこの技法を学んだとされています。
見出しに戻る
▶︎ パリ画壇に絶賛された技法とは!?
藤田嗣治(レオナール・フジタ)《シーソー》(1919年、公益財団法人諸橋近代美術館)
1913年に初めてパリを訪れた藤田は、西洋美術の本質に迫ろうとその源流や歴史を研究する一方で、当時パリを席巻していた前衛芸術に接近し、ピカソやアメデオ・モディリアーニ(1884-1920)らといった画家たちと親交を深めていきます。交流のなかで様々な影響を受け、試行錯誤の末、紙や絹の質感を油彩で再現することを思いつき、西洋と東洋の美術を融合させた独自の画風を確立させます。特にお手製のカンヴァスの上に日本画用の面相筆と墨で細い輪郭線を引き、繊細な陰影を施した裸婦像は、「素晴らしき白い地[grand fond blanc]」や「素晴らしき乳白色」と称され、パリ画壇に絶賛されます。この「乳白色」*¹の肌は、のちに藤田作品の代名詞にもなりました。
*1この乳白色の成分は、近年の分析では「水性と油性が混在した多層構造」*aとなっており、「細目で平織りの麻布に膠の目止め剤、次に鉛白と炭酸カルシウム(または石膏)に膠と乾性油を混ぜた半油性(エマルジョン)の地塗り、その上にタルク(ベビーパウダー)を塗布している」*bと今日では指摘されています。
*a*bともに、三木学「フジタ−−「色彩」と「質感」の旅」(展覧会カタログ『フジタ—色彩への旅』(ポーラ美術館)2021年)より引用
見出しに戻る
▶︎ 過酷な撮影現場
フィリップ・ハルスマン《官能的な死》(1951/2020年、公益財団法人諸橋近代美術館)
ダリとハルスマンは1週間かけてモデルの選考作業を行い、予備のモデルも含めて頭蓋骨の構造に相応しいプロポーションの9名が用意されました。撮影の当日、ハルスマンがシャッターを切るまでの準備には、実に4時間以上を費やしました。ダリの原画を忠実に再現するために幾度となく測定と調整を繰り返す一部始終は、コンタクトシートからも窺い知ることができます。モデルたちが過酷な体勢を長時間維持することはできないので、実際にハルスマンがシャッターを切ったのはほんの数回であったとされています。
見出しに戻る
▶︎ 作り方は単純明快!
フィリップ・ハルスマン《ダリ爆発》(1953/2020年、公益財団法人諸橋近代美術館)
この写真は、事前に準備されたダリのポートレートのネガを映写機に取り付けて牛乳入りの皿に投影し、石を投下して飛沫が上がった瞬間を捉えています。この“爆発”を起こすには牛乳が持つ液体粘度が最適であるとして、ハルスマンが制作に用いました。
見出しに戻る
▶︎ ヘリコプターでそんなことを!?
フィリップ・ハルスマン《ポルト・リガト・ヘリコプター》(1964/2020年、公益財団法人諸橋近代美術館)
まるでヘリコプターから飛び降りた瞬間をとらえたように見えるこの写真は、アクリル板のステージ上でポーズをとるダリを下から撮影しています。ダリが口ひげの先端を小型のヘリコプターに結んで浮遊しているように見せています。
見出しに戻る
▶︎ 体を張ったダリにも注目!
フィリップ・ハルスマン《私は原子爆発に思いふける》(1954/2020年、公益財団法人諸橋近代美術館)
様々な状態の口ひげを撮影するために、ハルスマンは水槽の中に頭を漬けるようダリに頼みました。いつもはピンと上を向いたひげが水中でふにゃふにゃと揺蕩う様はそれだけでも面白いものの、ハルスマンはそれだけでは満足せず、口に牛乳を含むようダリに依頼します。ダリが再び頭を水に漬けて牛乳を吐き出したところを撮影し180度反転させると、まるでダリの口からキノコ雲が立ち昇っているような視覚効果が生まれたのでした。
見出しに戻る
▶︎ この時代は全部アナログ
フィリップ・ハルスマン《マリリン・マオ》(1967/2020年、公益財団法人諸橋近代美術館)
この写真は、ダリがハルスマンに「毛沢東主席のように見えるマリリンが見てみたい」と相談したことから制作されました。仕掛けは至って単純なもので、ハルスマンはマリリンと毛沢東それぞれのポートレートを準備し、慎重に引き伸ばしと切り貼りを繰り返すことでダリの突飛な願いに応えてみせました。
見出しに戻る