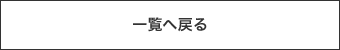2024年12月01日 更新
▶︎ 伝説の恋人たち
マリー・ローランサン《ダンサー》(1928年、公益財団法人諸橋近代美術館)
23歳でモンマルトルにあるアトリエ「バトー=ラヴォワール(洗濯船)」を出入りするようになったローランサンは、ここでピカソと知り合います。ある日、ピカソの個展に出かけた際に、彼の親友で偉大なる詩人ギヨーム・アポリネール(1880-1918)を紹介され、二人は一目で恋に落ちます。アポリネールの小説『虐殺された詩人』内に記されている一節は、二人が出会ったときのエピソードをモチーフにしていると言われています。ローランサンの私生活と画業において、アポリネールの存在は多大な影響を及ぼしたと言っても過言ではありません。当時、女性で職業画家になることは難しいことでしたが、アポリネールのサポートと期待のおかげでローランサンの作品が高水準を保ち続けていたことは明らかです。アポリネールもまた、ローランサンの人柄だけでなく才能にも惚れ込み、彼女を新進画家に育て上げるとともに、彼女との恋から生まれたとされる最も美しい詩『ミラボー橋』を手がけるなどします。
恋人だけに留まらず互いの芸術においても刺激し合う関係性にあったことは事実ですが、次第にすれ違いを見せるようになっていきます。アポリネールが容疑者となり勾留された「モナ・リザ盗難事件」、そして最愛の母の死が決定打となり、二人は破局します。これにより恋人という関係性は終局を迎えますが、その後も手紙のやり取りは続けていきます。ローランサンの遺言により、彼女は死後、アポリネールから送られた手紙の束と1本の薔薇とともに、彼と同じ墓地に埋葬されました。
見出しに戻る
▶︎ 画家と画商の関係
ジョルジュ・ルオー《流れる星のサーカス》(1934-38年(1938年刊行)、福島県立美術館)
20世紀の画家を語る上で大画商ヴォラールの存在は欠かせません。19世紀後半から20世紀前半にパリで活躍したヴォラールは、1893年にパリで画廊を開いて以来、セザンヌ、ピカソ、フォーヴィスムのグループといった今日では名だたる画家たちの作品を、彼らの名がまだ知られていない頃から紹介し、絵画をただ売るだけでなく、ときにはプロデューサー的な役割も果たし、国内外に彼らの知名度を高めるなど多大なる貢献と影響を及ぼしました。
ルオーもまたヴォラールに見出され、1907年に初めて作品の注文を受けます。1917年にはルオーのアトリエの全作品をまとめて購入し、ルオーの専属的な画商となりました。以降、ルオーとヴォラールの関係性はヴォラールが死去するまでの30年間以上続き、この間にルオーの代表作『ミセレーレ』や『ユビュおやじの再生』が制作されます。ルオーの特徴ともいえる重厚感のある油彩や豊かな色彩もこの時期から見せ始めることになります。
見出しに戻る
▶︎ 試行錯誤の末に…
ピエール=オーギュスト・ルノワール《モーリス・ドニ夫人》(1904年、公益財団法人諸橋近代美術館)
ルノワールもまた、大画商アンブロワーズ・ヴォラールと深い信頼関係にありました。ヴォラールはルノワールへ助言するほか、作品を売却したり個展を開催するなど、ルノワールを物理面だけでなく精神面でも支えた人物でありました。1883年、ルノワールはヴォラールに「印象主義で行き着くところまで行った」*¹と述懐しています。事実、この時期の作品には試行錯誤の跡や画風の展開が見受けられますが、これは1881年から82年のイタリア旅行がきっかけであるとされ、以降は古典的な表現を模索しました。本作でもこの古典的な表現に通じる描写が見受けられます。ドニの希望によって制作された本作は、ドニが傾倒していた初期ルネサンス期の肖像画を想起させます。一方で、簡潔な表現と頭部を頂点にした三角形の安定した構図、色彩の効果からは、古典絵画といった過去の美術の研究が反映されていることがうかがえます。
*1 Ambroise Vollard, En écoutant Cézzane, Degas, Renoir, 1938 [2003], Grasset, p.295
見出しに戻る
▶︎ 貧困に苦しみながらも描き続けた美しい風景
アルフレッド・シスレー《積み藁》(1895年、公益財団法人諸橋近代美術館)
元々は実業家の道に進むためにロンドンへ訪問しますが、同地でターナーやコンスタブルといったイギリス絵画に触れ、パリに戻りエコール・デ・ボザール(国立美術学校)に入学します。イギリスの偉大なる画家であるターナーやコンスタブルたちだけでなく、シスレーはコローにも影響を受けていたといわれています。裕福な家庭で育ったため、父親の援助もあり経済的にも恵まれた環境下で画業に勤しんでいましたが、1870年に普仏戦争が勃発すると父親の事業が破産します。自身の絵を販売するしか生計を立てる手段がありませんでしたが、シスレーの作品はあまり評価されなかったことから、残りの生涯を貧困の中で過ごすことになりました。経済的にも苦境に悩まされ続け、ついに1880年に画商デュラン=リュエル(1831-1922)と安定した経済的支援を引き換えに絵を手放す契約を結びます。のちにシスレーはピサロにデュラン=リュエルのことを最悪の敵だと述べたと言われています。以降、ロワン川沿いの小村を転々としながら長閑な風景画を制作し、1882年になると本作の舞台となるモレ=シュル=ロワンに移住します。この頃から咽頭癌の兆候があらわれるようになり、制作が困難となり生活はさらに逼迫した状況となりますが、それでも貧しい暮らしの中で印象派の手法を保ちつつ制作を続けていきます。シスレーはその生涯を印象派に捧げたといっても過言ではないでしょう。
見出しに戻る
▶︎ 一攫千金大チャンス
アルマン・ギヨマン《アゲイ湾》(1910年、公益財団法人諸橋近代美術館)
ギヨマンは収入が少なく生計を立てるために仕事と絵画制作を両立した生活を送っていました。15歳のときには叔父が経営する店で働きながら夜間に絵の勉強をし、18歳にはオルレアン鉄道会社に勤務する傍ら絵を描いていました。20歳で画塾アカデミー・シュイスに入るとそこでセザンヌとピサロと出会い親交を深めます。この三人の画家は頻繁に行動を共にし、ギヨマンとセザンヌに至っては一時期隣同士でアトリエを構えていたほど終生の仲だったとされています。画塾で学んでもなお、絵だけでは生計を立てることはできず、27歳でパリの土木課の夜間業務に勤務し、日中を絵画制作に当てる生活を送ります。1891年、ギヨマンにとって転機が訪れます。なんと宝くじが当選し、10万フランもの大金を得たのでした。一気に安定した生活を手に入れたギヨマンは、仕事を辞め画業に専念します。以降、フランス中を旅し、遠方へ積極的に足を運ぶようになったギヨマンは、画家の道を進み続け、誠実に絵画と向き合った人生を送りました。
見出しに戻る
▶︎ 親友が義父に…
モーリス・ユトリロ《モンマルトルのソル通り》(1914年、公益財団法人諸橋近代美術館)
ユトリロは他の誰からも画家としての正規な指導を受けず、ましてや美術学校や無数あったアトリエにも通っていません。幼い頃からアルコール依存症に悩まされた彼は、21歳でパリの精神病院に強制的に入院させられます。4ヶ月間の入院生活を送り、退院後に対症療法として絵を描くことを勧められ、母親は息子に絵筆を取らせたのでした。
ユトリロには奔放な母親がおり、この母親が恋した人物はなんと自分の親友(3歳年下の画家)でした。当時23歳だったユッテルに夢中になった母親は、すでに40代半ばに達していましたが、夫と離婚後、正式に結婚します。こうしてユッテルはユトリロの親友から義父となり、ユトリロの作品売買に尽力するようになります。
見出しに戻る
▶︎ あのルノワールとの関係も…
ジャン=バティスト=カミーユ・コロー《ヴィル=ダヴレーの池(洗濯女たちと水飼場に来る馬)》(1847年、栃木県立美術館)
コローはしばしばバルビゾン派の画家の一人としてみなされることがあります。というのも、コローの師であるベルタンやミシャロンが新古典主義の歴史風景画家と称されることから、その次世代に登場したバルビゾン派に安易に分類されてしまうのです。しかし、詳細に見ていくと年齢的にもバルビゾン派よりも前に活躍した風景画の立役者たちに属し、かつ先人たちに学んだことから、印象派へと続く自然主義的な風景画世代への橋渡しとして位置していたことが今日では指摘されています。事実、印象派の画家たちからは「コロー爺さん」と呼び慕われ、若き画家たちに助言を授けていたとされています。その一つがルノワールとの関係です。ルノワールの風景画にはシスレーやピサロといったほかの印象派の画家たちと比べ、薄塗りのタッチが重なり合う絵具の効果から、靄のかかった表現が顕著にあらわれています。《パリ郊外、セーヌ河の洗濯船》(展示中)でもその効果が見られます。移ろう自然光をそのまま画面に定着させる難しさと、戸外のもとで描いた画面をアトリエで見返すと醜悪なものなってしまうことを悩んでいたルノワールは、コローに戸外で制作する難しさを相談しました。するとコローはこう助言しました。
「それはね、外では自分が何をしているか確信が持てないからですよ。必ずアトリエで描き直さなければならないのです[C’est que, me répondit-il, dehors, on ne peut jamais être sûr de ce que l’on fait. Il faut toujours repasser par l’atelier.]」*²
コローの風景画を見ると、戸外でのスケッチをもとにアトリエで制作しているにも関わらず、現実の一場面を切り取ったかのような正確な観察に基づいて描かれているのがわかります。サロンで成功を収めた大家であり、自然観察に基づく風景画によって世間にひろく認められていたコローは、ルノワールをはじめとした若き画家たちにとっての希望であり、心強い先達であったことは間違いなかったことでしょう。
*2 Ambroise Vollard, En écoutant Cézanne, Degas, Renoir [1938], Paris, Grasset, 2003, p.214
見出しに戻る
▶︎ 時代に翻弄された少年時代
ベン・シャーン『ドレフュス事件』(1930年(1984年刊行)、福島県立美術館)
シャーンは8歳のときに父親が革命活動の容疑でシベリア送還となり、故郷から逃れることを余儀なくされ、ニューヨークに移住します。芸術家としての初期時代からソーシャル・リアリズムの様式を体現し、当時の政治的腐敗や社会問題といったテーマを描いていました。特に「サッコとヴァンセッティ事件」*³、「ドレフュス事件」(題材によりみちで解説)を題材にした作品は、シャーンの注目を集めます。シャーン自身も移民であり、不正や抑圧に対して強い嫌悪感があったことから、彼の作品にはそれらに対する明確な拒絶の表現が如実に描写されています。シャーンは雑誌『タイム』(1967年9月15日)で以下のように述べています。
「私が描くものは2つ。自分が愛するもの、そして自分が嫌悪するものだ。[I paint two things: what I love and what I abhor.]」*⁴
*3 1927年にマサチューセッツ州で起きた強盗殺人事件の容疑にかけられた2人のイタリア人移民バルトロメオ・ヴァンセッティとニコラ・サッコが、不十分な証拠のみで処刑された事件
*4 “Painting: Mellowed Militant,” Time, September 15 1967, https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,941166,00.html
見出しに戻る
▶︎ 伊達男パスキンの生涯とは?
ジュール・パスキン《帽子を持つ少女》(1924年、公益財団法人諸橋近代美術館)
パスキンの作品では、退廃、倦怠感、孤独感などが感じられることがしばしば指摘されますが、これは彼自身が抱えていた感情が映し出されていると考えられています。パスキンは20歳でパリに移住する前から既に名が通っていたこともあり、モンパルナスの芸術家たちのなかでもリーダーに据えられるほどの存在でした。いつも黒い服と山高帽を身につけ、白いシルクのマフラーを巻いており、「照れくさそうな雰囲気とは裏腹に、鋭い眼光を持つ」まさにモンパルナスの王子という名にふさわしい伊達男だったのです。
そんなパスキンには妻エルミーヌのほかにリュシーという恋人がいました。二人の関係を察知したエルミーヌは身を引くことを決意。しかし、リュシーもまた夫と子どもを捨てることができず、彼女と結婚したいというパスキンの願いは結局叶いませんでした。意外にもエルミーヌとリュシーの関係は良好で、時には三人で行動を共にしたこともありましたが、パスキンはその関係性に苛立ちを募らせていたとされます。1930年6月2日、パスキンはモンマルトルのアトリエで首を吊って命を絶ちます。原因は未だ不明ですが、浴室の壁には自ら剃刀で切ったであろう手首の血でこう書かれていました。
「ADIEU LUCY(さよなら、リュシー)」
見出しに戻る
▶︎ 殺人事件の容疑者に…!
イヴォンヌ・ハルスマン《インタビュー》(1954/2020年、公益財団法人諸橋近代美術館)
ハルスマンが22歳のとき、オーストリアでのハイキングに同行していた父親が殺害される事件が起こります。当時、この地域では反ユダヤ主義傾向が高まっており、地元当局は証拠や動機もないままユダヤ人の息子のハルスマンを逮捕します。父親殺害の罪で起訴され、懲役刑が宣告されますが、即座にオーストリアとドイツ全土の学者たちから異議が唱えられ判決は棄却。この抗議で事件は差し戻されますが、2審で有罪となり懲役刑が課せられました。服役後、この事件がきっかけでオーストリアを離れ、パリに移り、写真家としてのキャリアをスタートします。モンパルナスに自身のスタジオを構え、従来の肖像写真を打ち破るシャープで大胆な写真で一世を風靡し、その後もキャリアを順調に構築していきます。しかし、ナチスによるパリ侵攻が起きると、友人アインシュタインの仲介もありアメリカに亡命。同地では仕事を通じて20世紀を代表する多くの著名人と対面する機会を得ます。なかでもダリとは37年にも渡る協働制作で多彩でユニークな写真を次々と生み出しました。
見出しに戻る