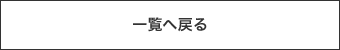2024年12月01日 更新
▶︎ キュビスムはいつ登場したの?
パブロ・ピカソ《戦士 1962年10月28日》(1962年、公益財団法人諸橋近代美術館)
1905年に開催された「サロン・ドートンヌ[Salon d’Automne]」において、のちに「フォーヴィスム」と呼ばれる画家たちの作品が展示され、大きな話題を呼びました。それまでの光学理論に準じて理知的に色彩表現を施す新印象派を越えるべく、感覚的に色彩を用いて描写することで、色彩を固有色から解放し、美術界から注目されます。これにより、20世紀という新たな時代とともに革新的な芸術運動が幕を開けることとなりました。これに続くかのように前衛芸術はさらに加熱していき、20世紀を代表する前衛芸術「キュビスム」もこの時期に誕生します。
キュビスムという名が初めて呼ばれたのは、1908年にジョルジュ・ブラック(1882-1963)の作品が画家マティスと批評家ルイ・ヴォークセル(1870-1943)に「小さな立方体」と例えられたことからだとされます。キュビスムが革新的と謳われたのは、西洋美術の伝統的な手法からの脱却に果敢に取り組んでいたことにありました。特にピカソは、ルネサンス以来の伝統的な絵画技法(線的遠近法や陰影法による空間表現)を、単純な幾何学的な形態と陰影を組み合わせることで立体感を表現する探究を試みました。ピカソやブラックが行った造形表現の探究は、のちの芸術家たちによってさらに深められ、20世紀芸術のなかで多様に展開していきました。
見出しに戻る
▶︎ ナビ派ってなに?
ピエール・ボナール《水浴する女達のいる森の風景 》(1899年、公益財団法人諸橋近代美術館)
1880年代後半から90年代にかけてのパリでの芸術の流れは象徴主義に傾斜していきました。世紀末に近づくとブルジョワ階級が支配する社会の価値観に反発し、観念や感情といった人間の奥底に眠る魂の本質を表現しようとする芸術が開花していきます。そのため、世紀末から20世紀初頭にかけてのパリは、さまざまな芸術潮流が混在する状況でした。特に世紀末のパリでは秘密結社的な雰囲気をもつ芸術集団が二つ存在しました。そのうちの一つこそ「ナビ派」です。
ヘブライ語で「預言者[nabiya]」に由来するナビ派は、1888年10月にポール・セリュジエ(1864-1927)がゴーガンの教えを受けて描いた作品を、アカデミー・ジュリアンの画家仲間たちに見せたことをきっかけに誕生します。中心メンバーにはボナールも含まれていました。ナビ派の画家たちはゴーガンの総合主義はもちろん、セザンヌの造形性、ルドンの象徴主義などにも敬意を表し、絵画における自然主義や現実模倣よりも、装飾性と抽象化を志向しました。ナビ派の画家たちが扱う主題は各々異なり、画家たちの個性や主観性が作品に如実に出ていますが、線と色の調和のとれた総体こそ絵画であるというナビ派の基本的な考え方が表現されているのです。
見出しに戻る
▶︎ 新たな美の概念が誕生!
ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー《ストーンヘンジ》 (1829年、郡山市立美術館)
18世紀後半はイギリスで産業革命が進んだ時代であり、人が作り出す科学技術の力と人智を越える自然の脅威に画趣を見出す新たな感性が生まれた時代でもありました。特に「ピクチャレスク[picturesque]」と「崇高[sublime]」という美学は、風景に対する人々の意識を大きく変える要因となります。従来の滑らかで整った「美」に対し、壮大さや荒々しさ、不規則性などに美的価値を認める感性によって画家たちは風景をとらえていきました。
ターナーの地誌的風景画にはしばしば建築物が描かれますが、これは風景の中の空間を区分し、対象に目を導くための効果も兼ね備えていました。本作においても、荒天のもとに壮大な石柱を配置し、前景には雷に撃たれ倒れた羊の群れと羊飼いを描くことで鑑賞者の視点を各対象へ誘導する効果が如実に現れていることがうかがえます。
見出しに戻る
▶︎ イギリスで大流行、「グランド・ツアー」!
リチャード・ウィルソン《アクア・アチェトーサ》(1754年頃、栃木県立美術館)
18世紀のイギリスにおける教育的習慣として、貴族や上流階級の子弟の多くは外国語を学び、一流の芸術や古代遺跡などの異文化に触れ、教養を高め、洗練したマナーを身につけることを目的に、ヨーロッパ大陸に数ヶ月から数年にかけて滞在する大周遊旅行「グランド・ツアー[The Grand Tour]」が通過儀礼でした。特にイタリアはグランド・ツアーの重要な目的地として人気を博し、旅行者が帰国時に旅の記念品として持ち帰った景観画「ヴェドゥータ[veduta]」は風景画への関心を一層高め、美術制作に大きな影響を与えました。
ウィルソンもまた、1750年からのイタリア滞在をきっかけに風景画家に転向し、帰国後も滞伊中に学んだことを実践したことから「イギリス風景画の父」とも称されています。彼が描いた古典的風景と地誌的風景を融合した作品は、イギリスにおける風景画のジャンルの地位を高めたとしています。
見出しに戻る
▶︎ 「未完成作」こそ「完成作」!?
ピエール=オーギュスト・ルノワール《パリ郊外、セーヌ河の洗濯船》(1872-73年、公益財団法人諸橋近代美術館)
19世紀のフランスはまさに「革新」と「再生」の激動の時代でありました。若い画家たちは神話や聖書といった古典的な主題を扱う歴史画こそ尊いものとして重んじてきた美術アカデミーに抗議の意を表し、従来の制約から脱するべく、風景画や風俗画など日常生活にある情景といった卑俗とされた主題を扱う絵画が多く登場しました。また、このは、鉄道網の発達やチューブ式絵具が普及し、戸外制作が容易となり、彼らはアトリエの外へ足を運ぶようになります。
この中にはルノワールやモネらのちの印象派の画家たちも含まれ、当時のパリでは画家や文学者、批評家たちが白熱した議論を交わす集会が度々行われました。彼らはのちに「画家、彫刻家、版画家等の美術家による共同出資会社」というグループ名で第一回展を主催しますが、記者の蔑称により「印象派」として今日までひろく知られています。戸外制作を積極的に行った印象派の特徴としてしばしば指摘される、眼前の一瞬の情景を一気に画面に描き込む手法は、基本的に前世代の踏襲でありますが、彼らの革新性はそれまで習作とされていた「未完成作」を「完成作」としたことにあります。このような美意識の転向によって、自由な感性に基づく視覚的な絵画が誕生したのです。
見出しに戻る
▶︎ 近代風景画の先達者
ジャン=バティスト=カミーユ・コロー《ヴィル=ダヴレーの池(洗濯女たちと水飼場に来る馬)》(1847年、栃木県立美術館)
フランスにおける近代風景画の起源は19世紀初頭まで遡ることができます。この頃フランスではロマン主義が萌芽し、人間ドラマの表現を軸とした風潮が展開するなかで、風景画の領域でも新しい傾向が芽吹くようになりました。新古典主義の画家ピエール=アンリ・ド・ヴァランシエンヌ(1750-1819)は、画学生に向けた指南書『芸術家のための実用遠近法入門および画学生とくに風景画をめざす学生のための省察と忠告[Elémens de perspective pratique à l’usage des artistes, suivis de réflexions et conseils à un Elève sur la Peinture, et particulièrement sur le genre du Paysage]』(1800年刊行)のなかで自然観察の重要性を説き、その実践として戸外制作を奨励しました。ヴァランシエンヌの弟子であるアシル=エトナ・ミシャロン(1796-1822)とジャン=ヴィクトール・ベルタン(1767-1842)は師の教えに従い、野外でのスケッチを実践し、現実の光景から理想的な情景を創り出す手法を見出します。
この手法はコローへと継承され、ミシャロンとベルタンから学んだ自然に対する注意深い観察と忠実な描写は、コローの芸術形成の基礎を築きます。戸外制作で自然を瑞々しくとらえたコローの芸術は、のちの印象派へと続く次世代の風景画家たちの橋渡しとなりました。
見出しに戻る
▶︎ エコール・ド・パリとは?
マルク・シャガール《テルトル広場》(1953-54年、公益財団法人諸橋近代美術館)
20世紀初頭、パリのモンマルトルやモンパルナスには、フランス国内外のあらゆる地域から様々な画家たちが集結し自由奔放な生活を送っていました。今日では彼らは「エコール・ド・パリ(パリ派)」と総称され、特にシャガールやパスキン、藤田嗣治といった芸術家が挙げられます。彼らは特定のグループには属しておらず、様式などにはっきりとした方向性があったわけではありませんが、作品からは個性的な具象的表現の追求や、どこか哀愁のある表現がうかがえます。
エコール・ド・パリの芸術家たちはフランス以外の国からパリに移住してきたいわば外国人でありますが、この「エコール・ド・パリ」という言葉は、元々はパリを拠点とする外国人芸術家たちをフランス人芸術家「エコール・フランセーズ(フランス派)」と区別するために使われた名称でした。このことから「エコール・ド・パリ」という呼び方には、元々は排外主義的な意味が含まれていたことが指摘されています。
見出しに戻る
▶︎ フォーヴィスムってなに?
キース・ヴァン・ドンゲン《ボアを纏った女》(1925年頃、公益財団法人諸橋近代美術館)
20世紀前半のフランス美術の展開に大きな役割を果たしたのは、「アンデパンダン展[Salon des Indépendants]」と「サロン・ドートンヌ[Salon d’Automne]」といった権威やアカデミズムに寄らない展覧会でした。特に1905年10月に開催されたサロン・ドートンヌでは、マティスやドランといった画家たちの作品が出品され、彼らの前衛的な表現は強烈な印象を与えることになります。この展覧会に参加した批評家は、大胆な筆触や原色を多用した鮮やかな色彩表現に狼狽し、彼らを「フォーヴ(野獣)たち」と嘲笑を込めて命名しました。
この展覧会にはヴァン・ドンゲンも2点出品しており、激しい批評を受けることになります。以降、フォーヴィスムの画家たちはセザンヌの芸術から影響を受けると、空間構成に対する疑問を抱き、純粋な色彩を用いることを放棄します。一方、ヴァン・ドンゲンは彼らとは対照的に、色彩への探究と光への関心から自己研鑽を追求し続けました。これによりフォーヴィスム特有の強烈な色調を保ちながらも表現に富んだ独自のスタイルを確立することになります。
見出しに戻る
▶︎ 写真技術の誕生
イヴォンヌ・ハルスマン《インタビュー》(1954/2020年、公益財団法人諸橋近代美術館)
写真技術が公式に発表されたのは1839年。フランスのルイ=ジャック=マンデ・ダゲール(1787-1851)によってダゲレオタイプ*¹が発明されたことで、写真術という視覚メディアが誕生しました。その後、イギリスのウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット(1800-1877)が考案したネガ・ポジ反転方式のカロタイプ*²が発表され、複製技術としての写真が広く普及するきっかけとなりました。写真の再現性の高さと精緻さは当時の画家たちに衝撃を与え、反写真運動を支持していた画家ドミニク・アングルは、写真を禁止するようフランス政府に抗議したほどでした。写真の発明により、現実描写に重きを置く絵画の需要が少なくなると考えられたことは間違いありませんが、写真を活用していた画家がいたことも事実です。一方、後発の写真はあくまで「技術」として認識され、むしろ写真の方が絵画的な効果を追求し、「芸術」を目標としていた部分がありました。この動向は「ピクトリアリズム」と称され、わざとピントを外したソフトフォーカスが多用されました。
さらに20世紀になると、写真も写真でしか実現できない表現を確立していき、多様な技術が発展し、視覚メディアとして隆盛を迎えることになります。1920年後半になると小型カメラ「ライカA型」が登場したことで、写真が大衆化されます。シュルレアリスムもこの時期に勃興し、マン・レイ(1890-1976)やフランツ・ロー(1890-1965)らが多彩な形で写真術を展開しました。
*1 銀メッキされた銅版の上に画像を形成した撮影技法。解像度が高く、美しく鮮明で、見る角度によってポジにもネガにも見える。主に肖像写真に多用され、当時大流行した写真術。
*2 紙と支持体とした感光材料による撮影技法。ダゲレオタイプより鮮明さを欠くが、建築物や風景などの記録だけでなく、肖像写真にも多用された。単一の原板から多数の印画が作れるというメリットがある。
見出しに戻る